9月度 関西支部運営部会講演会
運営部会では、9月10日(水)の本会議終了後に、関西電力株式会社 IT戦略室長の上田晃穂理事をお招きし、講演会を開催しました
挑み続ける、関西電力。
関西電力は2025年に日本データマネジメント・コンソーシアムが主催する「データマネジメント大賞」を受賞された実績を持つ企業で、上田理事は経済産業省の人材育成に関するタスクフォース委員や関西大学の客員教授も務めています。
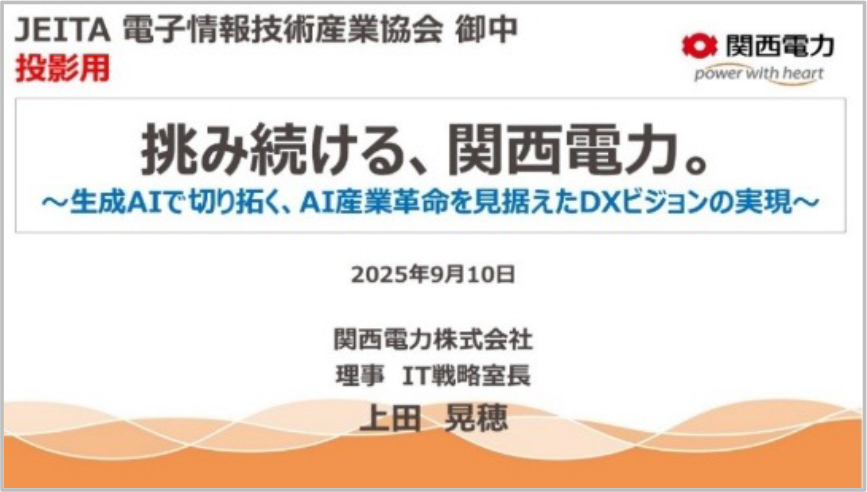

2030年AI産業革命を見据えた戦略的転換
本講演では、「挑み続ける、関西電力。~生成AIで切り拓く、AI産業革命を見据えたDXビジョンの実現~」と題して、2030年に到来するAI産業革命を見据え、同社が「AIファースト企業」となることを目指し、DX戦略を再構築した経緯が語られました。これは、従来の「日本の伝統的企業JTC(Japanese
Traditional
Company)」が「人の仕事プロセス」を変えずに部分的にAIを利用するのに対し、AIを前提として「人間が何に特化し、何をAIに任せるか」を想像してから業務を再構築する(AI First
Company)という根本的なパラダイムシフトです。経営スタイルも、計画重視の「フルマラソン型」から、環境変化に応じて方向修正を繰り返す「100m×422本ダッシュ」のアジャイル経営へと移行しています。DXを中期経営計画達成のための手段と位置づけ、人材・体制、データ、AIガバナンスを基盤とし、組織風土改革を重視する同社の戦略が詳細に解説されました。特に、AIを前提とした業務再構築や、DX人材の育成(全社員対象のDXリテラシー研修や高度DX人材育成)、人事制度との連携、そして「心理的安全性」を確保した挑戦する組織風土づくりへの取り組みなど戦略的に組織への浸透を図っていった経緯が紹介され、また、セキュリティ部門はDX推進の「ブレーキ」ではなく、安全な方向に導く「ガードレール」としての役割を担うべきであると強調されました。
AI活用事例としては、火力発電所での巡視点検ロボットや自律飛行型ドローンによる煙突内部点検、水力発電所での流氷雪自動検知システムなど、具体的な成果が紹介されました。さらに、社内ヘルプデスク業務の高度化、プレスリリースやQ&Aの自動作成、そして「社長AI」による経営意思決定支援といった、生成AIの先進的なユースケースも披露されました。DX推進状況として、2018年度から2024年度までに610件のPoCを実施し、そのうち473件が実用化され、2024年度のDX効果額は驚くべき数値が報告されました。
 その後の質疑応答では、参加者から「AIを前提とした業務再構築の浸透方法」や「DX推進における投資対効果の測定」について質問が寄せられ、上田理事からは、初期のやる気ある層(2割)に注力しボトムアップの動きを促すこと、ROIは直接・間接効果を複合的に見て追跡することなど、実践的な回答が提供されました。会合の最後には懇親交流会も開催され、参加者間の活発な情報交換と交流が深められました。
その後の質疑応答では、参加者から「AIを前提とした業務再構築の浸透方法」や「DX推進における投資対効果の測定」について質問が寄せられ、上田理事からは、初期のやる気ある層(2割)に注力しボトムアップの動きを促すこと、ROIは直接・間接効果を複合的に見て追跡することなど、実践的な回答が提供されました。会合の最後には懇親交流会も開催され、参加者間の活発な情報交換と交流が深められました。