第105回 機器・部品メーカー懇談会
関西支部・部品運営委員会では、6月18日(水)に標記懇談会をハイブリッドで開催しました。
部品運営委員長挨拶
 開会にあたり、小澤正人 2024年度委員長(パナソニック インダストリー(株)社長)より挨拶がありました。
開会にあたり、小澤正人 2024年度委員長(パナソニック インダストリー(株)社長)より挨拶がありました。
「今回の会合では、米国情勢、EV、宇宙の3つのテーマでご講演をいただきます。これらの講演は、皆様にとって多角的な視点から現状を理解し、将来を考える上で貴重な機会となるはずです。ご質問等ございましたら、活発な議論にご参加いただけますようお願い申し上げます」と述べられ懇談会がスタートしました。
トランプ政権の政策と日本企業への影響
ジェトロ本部調査部 米州課
課長 伊藤実佐子 氏
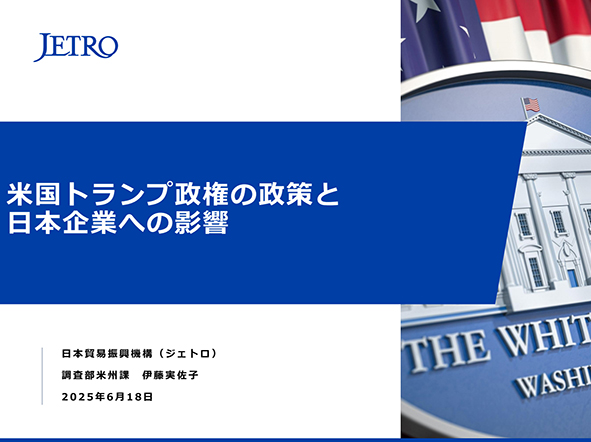
 トランプ政権の関税政策の概要、日本企業への影響、米国マクロ経済環境、そして今後の展望と対応策について説明します。
トランプ政権の関税政策の概要、日本企業への影響、米国マクロ経済環境、そして今後の展望と対応策について説明します。
トランプ政権は、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく相互関税(ベースライン10%)や国・地域別の追加関税に加え、通商拡大法232条に基づく自動車・部品、鉄鋼・アルミ製品など品目別の関税措置を発動しています。日本へは24%の関税が想定され、特に機械機器、中でも輸送機器や部品への影響が大きいです。ジェトロの調査では、日本企業の8割がベースラインの相互関税に懸念を抱き、多くの企業が価格転嫁やコスト吸収で対応する一方、サプライチェーンの組み換えは非現実的だと回答しています。ジェトロへの問い合わせも相互関税発表以降急増し、関税回避策の質問が増えています。
米国経済は個人消費が牽引し堅調で、失業率は4.2%と低い水準を維持しています。バイデン政権下のインフラ投資、CHIPS法、IRA(インフレ削減法)といった産業政策により国内製造業への投資が活発化し、日本は5年連続で対米直接投資最大の国となっています。
今後の展望として、IRA関連のEV税額控除廃止や水素製造へのクレジット停止、さらには予算案の「899条」(外国企業への課税強化)など、政策変更が注目されます。不確実性の中でも米国市場に戦略的に向き合うため、日本企業に対し、情報収集の強化、契約の見直し、USMCAなど既存の貿易枠組みの活用、ワシントンD.C.でのロビーイング強化が必要です。
電動車(テスラ・サイバートラック、Xiaomi・SU7等)分解により
見えてきた最新車載パワーエレクトロニクス技術と2030年における
車載部品に求められる技術要求仕様
名古屋大学 未来材料・システム研究所
教授 山本真義 氏
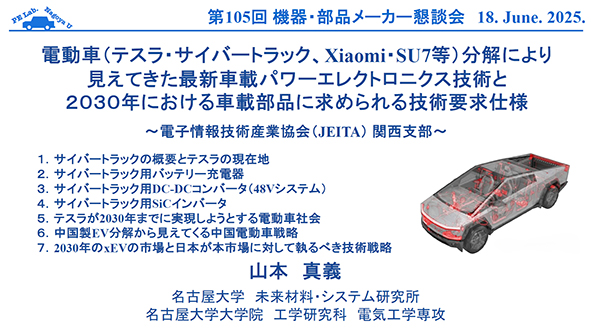
 EV市場の動向として、トヨタのバッテリーEV(BEV)販売が大きく伸びており、車両の価値が従来のハードウェアからソフトウェアやコネクテッド機能へと移行している点を強調したいです。半導体投資は産業機器、データセンター、自動車の3分野に集中しており、特にデータセンターではAIの電力需要増大に伴い、大電流に対応するパワー半導体の重要性が高まっています。
EV市場の動向として、トヨタのバッテリーEV(BEV)販売が大きく伸びており、車両の価値が従来のハードウェアからソフトウェアやコネクテッド機能へと移行している点を強調したいです。半導体投資は産業機器、データセンター、自動車の3分野に集中しており、特にデータセンターではAIの電力需要増大に伴い、大電流に対応するパワー半導体の重要性が高まっています。
自動車分野では、世界の市場がローカライズ化し、例えば中国では部品の65%を現地調達するなど、サプライチェーンの現地化が進んでいます。これにより車両価格は下がる一方、車両の付加価値が車両制御システム(SOC、MCU)へとシフトしており、日本企業はシステム全体を見据えた開発や、48V・800V系の新アーキテクチャ、樹脂やマグネシウムといった新素材を活用した冷却技術への投資が求められています。テスラのサイバートラックやシャオミSU7の分解例から、薄型インバーターや新しい冷却構造をご紹介します。また、トヨタRAV4がSiC(炭化ケイ素)を搭載することでインバーターの薄型化とバッテリー容量の増加、EV走行距離延長を実現した事例あります。
日本企業が競争の激しい市場で勝ち抜くためには、システム全体の理解と顧客要求に応じた開発、そして戦略的な投資が不可欠であると考えます。2027年頃に登場する新たなバッテリー技術によってEV市場が再び大きく成長すると予測され、日本が連携して市場を確保することが重要であると考えています。
宇宙開発利用の新潮流と宇宙ビジネスの将来像
東京大学 大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻
教授 中須賀真一 氏
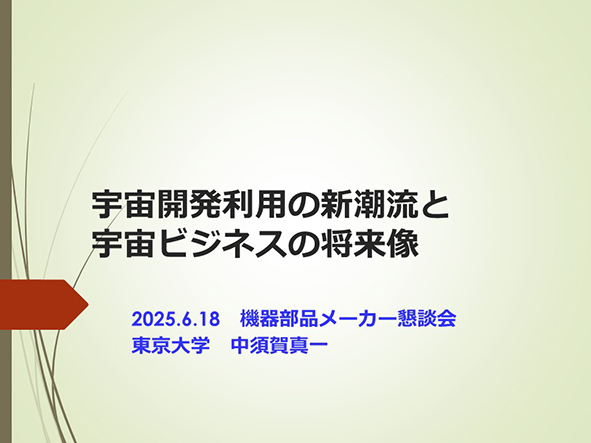
 宇宙産業は政府中心から民間主導へ大きく変化しており、日本もSLIM月着陸やH3ロケット成功、予算増(平成3年度の約2.5倍、6年度8945億円)など成果を上げています。高精度測位のQZSS(6cm精度)は自動走行・ドローン等へ活用され、地球観測のALOS(5mm精度)は地盤変動把握による災害・インフラ監視に応用されます。気象衛星ひまわりも豪雨観測機能強化でデータ活用拡大を目指します。月探査では、インドと連携し月面水資源の探査も計画されています。しかし、日本は「確実性」重視のため、新技術の実証不足、研究投資の遅れ、海外市場展開の弱さなどの課題に直面しています。宇宙戦略基金(10年で1兆円規模)による先端研究投資、民間主導の計画立案、グローバル連携、そして「1+aのN乗」で表される実証回数(N)の増加が不可欠と考えます。
宇宙産業は政府中心から民間主導へ大きく変化しており、日本もSLIM月着陸やH3ロケット成功、予算増(平成3年度の約2.5倍、6年度8945億円)など成果を上げています。高精度測位のQZSS(6cm精度)は自動走行・ドローン等へ活用され、地球観測のALOS(5mm精度)は地盤変動把握による災害・インフラ監視に応用されます。気象衛星ひまわりも豪雨観測機能強化でデータ活用拡大を目指します。月探査では、インドと連携し月面水資源の探査も計画されています。しかし、日本は「確実性」重視のため、新技術の実証不足、研究投資の遅れ、海外市場展開の弱さなどの課題に直面しています。宇宙戦略基金(10年で1兆円規模)による先端研究投資、民間主導の計画立案、グローバル連携、そして「1+aのN乗」で表される実証回数(N)の増加が不可欠と考えます。
2050年には宇宙産業の6割が「宇宙×他分野」の組み合わせで成長すると予測されており、他産業との連携や国際協力(特にアフリカ市場)が鍵となると思われます。地球のサステナビリティ(気候変動対策、宇宙太陽光発電)への貢献も重要視されています。大学発の小型衛星が宇宙革命のきっかけとなり、民生品活用・量産化、デジタルツイン活用による実証効率化も推進すべきと考えます。日本の宇宙ベンチャーは100社を超え、サービス調達モデルが世界的に活発化していますが、国内サプライチェーンの未完成も課題となっています。