第103回 機器・部品メーカー懇談会
関西支部・部品運営委員会では、6月14日(金)に標記懇談会をハイブリッドで開催しました。
部品運営委員長挨拶
 開会にあたり、坂本真治 委員長(パナソニック インダストリー(株)社長)より挨拶がありました。
開会にあたり、坂本真治 委員長(パナソニック インダストリー(株)社長)より挨拶がありました。
2019年度以来の委員長就任となります。この間、米中のデカップリングからロシアのウクライナ侵攻、生成AIの勃興まで、さまざまなことが起こりました。5年前に予測できたものは何一つなく、将来を見通す難しさを感じます。時代の変化に合わせていかに速やかに変われるか、が重要で、本日のご講演からそのヒントをいただければと、楽しみにしております。
世界で進むビジネスモデル変革
~多様化する世界とビジネス~
富士通(株) 松本国一 氏

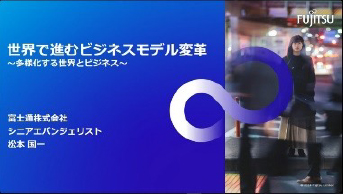 デジタル化が世界で急加速しています。年間12億台のスマホが出荷され、90兆GBのデータが生み出され、世界中どこにいても情報に触れ、発信する時代です。
デジタル化が世界で急加速しています。年間12億台のスマホが出荷され、90兆GBのデータが生み出され、世界中どこにいても情報に触れ、発信する時代です。
DXは“誰かのありたい姿をデジタルで実現すること”です。買物客にとってのDXはキャッシュレスやPOSでなく、並ばずに済むスマホレジです。DXを進めるには、最初に完成形を求めず、簡単なことから始め、利用者の体験を変えてゆくことが重要です。
デジタル化でものづくりのハードルも下がりました。XiomiがアリババRFQを駆使してEV生産に参入するまで3年しかかかっていません。専用部品の調達を求められる自動車生産のエコシステムは過去のものです。中国には500の自動車メーカーがあり、EV生産の上位9社は他業界からの参入です。アップルは、より市場価値の高いAIに特化すべく、コモディティ化した自動車を見限りました。
多様化した世界では、適時少量の生産が求められます。中国のオンラインファストファッション小売りSHEINはSNS上のトレンドをAIで分析、細分化されたニーズを早く知り、それを満たす商品を早く作り、早く売ります。デジタルの活用で、流行のファッションを安く気軽にすぐ手に入れる、というニーズに応えています。
日本のものづくりも、日本に限らず実現できます。IT機器ODMのJENESISで経営を担うのは日本人ですが、深?のサプライチェーンとアジャイルな開発・製造体制を活用しています。AIWAブランドの事業をはじめとする日本品質のものづくりは、日本人のニーズも満たすものです。
生成AIは専門知識の活用を可能にします。今後、より専門分野に特化したAIが次々に登場し、競争の場は、エンジンの開発から用途の提案に移ってゆくでしょう。
デジタルの活用が進めば、業界の枠すらも消えてゆき、最後に残るのは、コアとなる普遍的な強みだけです。それを活かすために何をなすべきか考える必要があります。変わらなければ必ず取り残されます。
縁の下の力持ち「クラウド」と歩む未来
アマゾン ウェブ サービス ジャパン(同) 梶本一夫 氏

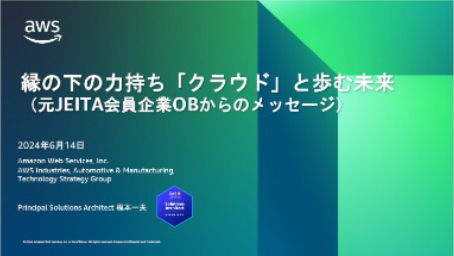 パナソニックで、デジタル家電の開発をはじめハードウェア中心のビジネスに携わった後、AWSで自動車産業のDXを推進しています。その立場からDXにおけるクラウドの重要性と日本企業が直面する課題についてお話ししたいと思います。
パナソニックで、デジタル家電の開発をはじめハードウェア中心のビジネスに携わった後、AWSで自動車産業のDXを推進しています。その立場からDXにおけるクラウドの重要性と日本企業が直面する課題についてお話ししたいと思います。
Amazonは“顧客満足”を行動原理とし、それは、よく知られたAmazon Flywheelに表現されています。AWSもこれを踏まえて事業を展開、独自スマホやスマートスピーカーなど失敗はあるものの、大きな成長を遂げました。
日本では、いまだにソフトウェアへの理解やITベンダーへの信頼が十分とは言えず、その結果、クラウド化において世界に大きく遅れを取リました。クラウド化を進めることで、コストの削減はもちろん、柔軟なインフラ運用も可能になります。
クラウドの活用により、大量のデータを低価格で保持する道が開け、ベンチャーによる大規模言語モデル(LLM)開発に拍車がかかりました。こうして生まれた生成AIについて、GoogleはGemini、MicrosoftはCopilotを柱に、いずれもB2Cメインで取り組みを進めています。AmazonはB2Bを戦略の中心に据えています。自動車産業向けでは、車両デザインの最適化支援、Alexa LLMテクノロジーによる車載インテリジェントパーソナルアシスタント、自動運転の開発に必須の膨大なデータにおける個人情報の秘匿、といったサービスを展開しています。
IT後進国である日本には、先行各国の成功・失敗から学べる利点もあり、大きな成長の余地があります。ソフトウェアは、必要悪としてのコストではなく成長に不可欠な投資で、それによる日本企業の進化が大きく期待される所です。
企業導入の鍵はAIリテラシー。
最新動向から読み解く生成AI時代の日本社会
(一社)生成AI活用普及協会 小村 亮 氏
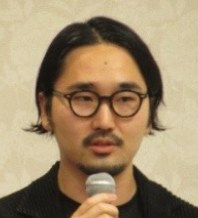
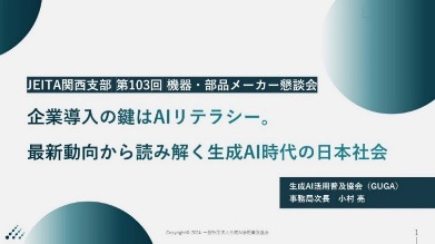 生成AIを巡っては多くのリスクが指摘されます。生成AI活用普及協会では、これを回避する一つの方策として、生成AIパスポート資格試験を推進しており今後、導入が本格化すると考えています。
生成AIを巡っては多くのリスクが指摘されます。生成AI活用普及協会では、これを回避する一つの方策として、生成AIパスポート資格試験を推進しており今後、導入が本格化すると考えています。
政府においても、内閣府のAI戦略会議は異例のスピードで進められ、広島AIプロセスによる国際的ルールの検討、AI関連予算の増加、AI知財検討会の推進、AI事業者ガイドラインの発信など、生成AIの重要性に関する認識は高まっています。
企業の活動においても、認知は進みつつありますが、活用に至る前段階で足踏みしている様子がうかがわれます。業務の効率化や新たなビジネスモデルの創出に大きな期待があるものの、リスクに対する懸念から、スキル以上にリテラシーが重視されています。製造業における生成AI導入については、過去に蓄積された独自データをいかに活用するかがポイントとなるでしょう。
生成AIの主なリスクとして、誤情報等との接触、個人情報の漏洩、知的財産権等の侵害、不正競争防止法への抵触が考えられます。これを管理するためには、個々の責任意識の醸成、適切な人材の配置と育成、評価制度の整備が必要です。
今後の社会では生成AIが人の仕事を奪うのではなく、活用できる人材が、活用できない人材の仕事を奪う構図となります。リテラシーとスキルの両面で、生成AIに関するリスキリングが求められます。
企業の生成AI導入においては人材の育成こそが鍵を握ります。生成AIパスポートは、そのための枠組みとなるものです。
DXと生成AIの最新動向とクラウド活用の必要性など、貴重なお話をいただき、非常に有意義な機会となりました。