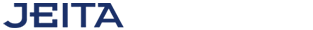スペシャルインタビュー第5回 楽天株式会社 楽天技術研究所 リードサイエンティスト 益子 宗 氏(1/2)

楽天株式会社はCEATEC JAPAN 2015特別企画「NEXTストリート」に出展します。
広報室取材班では、一足お先にその展示内容について楽天株式会社 楽天技術研究所 リードサイエンティスト 益子 宗 氏にお話しを伺いました。
ネット上の商品の人気度をリアルの世界で表現するHITOKE
ーーーQ.益子さん、CEATEC JAPAN 2015特別企画「NEXTストリート」でどのような技術を展示されるのでしょうか?
楽天技術研究所で開発した2つの技術を紹介します。
1つ目は「HITOKE」(ひとけ)という、商品の購買者属性や購買数といった商品の人気度可視化する技術です。
今回のNEXTストリートでは、Web版の「HITOKE」とスマートフォンおよびWebカメラを使った拡張現実版「AR HITOKE」の3種類を展示します。
例えば、現実の世界だと、行列のできているラーメン屋さんっておいしいんだ、というのが分かりますよね?「HITOKE」はまさに、ネットでもリアルであってもおいしいラーメン屋が一目で分かるという技術です。

▲商品の人気度が一目でわかる「HITOKE」
「HITOKE」では商品の購買情報を人型のアイコンで表現し、各商品上に表示します。アイコンは性別や年代で色相を変えているので、どういった層に人気のある商品なのか一目で分かります。
僕らは、この「HITOKE」の技術で商品の人気度を可視化し、それを見たユーザの購買行動にどんな変化が起こるのか考察しています。
以前、楽天のイベントでデモをした時に、沢山のアイコンが表示された商品に実際に注目が集まりました。そこで分かったのは、可視化はいい面もあるし、悪い面もある。例えば、人が並んでいない商品でも、すごくいいものはありますが、「HITOKE」ではまるで人気が無いように見えてしまうことがあります。だから、表現方法や、使いどころなど、まさに応用可能性を検討しているところです。
ーーーQ.「HITOKE」を開発するきっかけはなんだったんでしょうか?
「HITOKE」はもともと社内のビジネスコンテストで提案されたアイディアです。それを研究所でAR技術と組み合わせたものが「AR HITOKE」です。
最近、スマートフォンやタブレットなどが普及してきましたよね。インターネットの世界がPCだけで閉じる世界ではなくなってきていて、日常生活の様々なシーンで色々なデバイスを使ってリアルの世界からも自由にアクセスできるようになっています。
そうなってくると、購入者のレビュー情報や関連商品を見たりなど、これまでネット上でのみ可能だったユーザ体験をリアルの世界でもしたいというのはごく自然なことだと思います。ですので、そのようなネット上での体験をリアルの場でもユーザに提供したいという考えがベースにあり、「HITOKE」を開発することになりました。
ーーーQ.開発で難しいと感じたところはどこですか?

課題はまだまだあります。
実際にこうしたサービスをビジネスとして検討すると、スマートフォンを使いこなせるユーザがいっぱいいなきゃいけないとか、アプリのダウンロードに掛かる手間がネックになることがあります。
他にも、例えば、百貨店でデモをした際は、楽天が持つ消費行動分析データと百貨店のPOSデータを繋ぐ必要があったのですが、作り込みにかなりの時間が必要でした。また、現状の技術では1時間遅れの情報が表示されますが、これをリアルタイムで表示するには、開発コストに加え、時間もかかってきます。
また、eコマース特有の課題として、売上げのあるなしが顕著に見えるということがあげられますが、それをどのように見せていくかもポイントになってきます。「HITOKE」も単純に実際の購入数を表すのではなく、相対的なボリュームを表現するよう工夫しています。
どうやったらインタラクションを実現できるか
ーーーQ.2つ目の展示内容について教えてください。
2つ目は「WallSHOP」でデジタルサイネージを活用したプロジェクトの総称です。リアルの世界でもユーザとのタッチポイントを作っていこうという楽天の方針が背景にあり、開発された技術です。
楽天は、ネット上のみでサービスを提供してきたため、ユーザはインターネットにアクセスしないと商品情報を閲覧したり、購入したりできませんでした。
しかし、リアルの世界においても、こういうものを売ってるとか、こういったキャンペーンをやってますとか、商品情報を閲覧できる環境を作り出していきたい。それも、ただ商品情報をリアルの世界に出すのではなく、インタラクションを付加して新しいユーザ体験を生み出すことを同時に考えています。